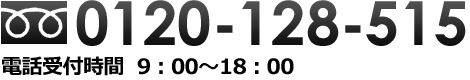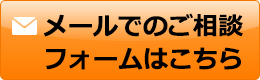「雨が“しとしと”降る」「お腹が“ぐうぐう”鳴る」「気持ちが“もやもや”する」。
普段、何気なく使っているこうした言葉、みなさんはどのくらい日常会話などで利用していますか?
このような言葉は「オノマトペ」と呼ばれ、大きく5つに分類できます。
| 分類 | 具体例 | |
| 擬声語(ぎせいご) | 動物や人の声を模倣した音 | ワンワン、ニャー、えーん |
| 擬音語(ぎおんご) | 自然や物の音を模倣した音 | ドーン、ザーザー、チクタク |
| 擬態語(ぎたいご) | 音のない動き・様子・状態を表現 | フワフワ、ニコニコ、キラキラ |
| 擬容語(ぎようご) | 見た目・形・質感を主に表す | つるつる、ざらざら、もこもこ |
| 擬情語(ぎじょうご) | 感情・心理的な状態を表す | イライラ、ワクワク、もやもや |
日本語にはなんと4,500語以上のオノマトペが存在するとも言われています
特に「擬容語」や「擬情語」は、日本語ならではの表現であり、英語や韓国語などの他の言語にはあまり見られない特徴です。
英語とオノマトペ
英語にも感情や感覚をオノマトペ的に表現する語がありますが、日本語ほど多用されてはいません。
例えば、「uh-oh(やばっ)」「meh(まあまあ)」「yikes(ひゃー)」「grr(イライラ)」「zzz(眠い)」などがありますが、これらは感情の発露や反応としての「間投詞」や「感嘆詞」に分類されることが多く、音を以って内面の感情や風景を表しているわけではありません。
日本語のオノマトペが生み出す“感覚共有”
日本語では、オノマトペだけで話者と聞き手の間に情景や感情を共有することが可能です。「感覚を音に変換する力」が日本人には備わっているとも言えます。
「チリチリ」…焦げるような痛みや熱さ
「ザラザラ」…手触り、喉ごし、記憶の断片的な質感
「フワフワ」…物理的な柔らかさと心理的な浮遊感の両方を同時に想像できる
どうでしょうか?たった一語で、その質感や情景が浮かんできますよね?
このように、日本語のオノマトペは「音の絵画」と表現しても良いかもしれません!
限られたコマの中で“情報”を伝える文化
日本の漫画やアニメは、限られたコマやシーンの中で豊かな感情や情景を伝えるという独特の文化を持っています。漫画では、コマの余白や表情の変化を通して感情を伝えることが多く、オノマトペがその効果を高めるためによく使われています。
漫画やアニメでの「音」が作り出す“没入感”
前述したように、漫画やアニメで用いられるオノマトペも会話と同様、ただの音ではなく、物語の進行やキャラクターの内面を視覚・聴覚で同時に感じさせる役割を果たしています。
限られたコマの中で、感情や情景をどう伝えるか。その描写には、想像以上に繊細な工夫や計算がなされているように感じます。
漫画やアニメが育む、音の感覚
日本では、漫画やアニメが日常に溶け込んだ文化として長く親しまれています。そんな環境の中で育つことで、私たちは知らず知らずのうちに、「音のない世界で音を感じ取る力」を身につけているのかもしれません。
こうした“感覚の共有”は、視覚的な文字表現が脳内で音や感情と結びつくことで生まれます。それはまるで、日本人ならではの感覚的な“特殊能力”のようにも思えるのです。