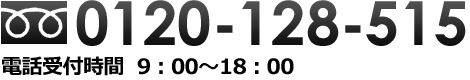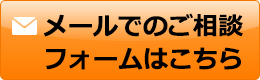キャスト陣の本気度に圧倒
驚いたのは、主要キャスト陣がこの映画のために1年半もの踊りの稽古を積んだという事実です。その徹底した準備と本気の取り組みこそが、あのクオリティを生み出していたのだと納得させられました。
その成果は、スクリーンを通じてもはっきりと感じ取ることができました。単なる「歌舞伎の真似事」ではなく、本物の歌舞伎役者としての風格と技術を身につけた役者たちの姿がそこにありました。
お稽古は、歌舞伎役者の四代目・中村鴈治郎氏(屋号:成駒家)が歌舞伎指導を施したとのこと。プロ仕込みとはいえ、所作や声色のどれをとっても、長年の修行を積んだかのような自然さと美しさがあり、観ているこちらも思わず息を呑むほどでした。
歌舞伎の女形に見る美学と奥深さ
役者全員が男性で、中でも女性役も演じ分ける「女形」は、歌舞伎の最も特徴的な要素の一つです。その繊細な所作や美しい立ち振る舞いは、現実の女性以上に女性らしさを体現していると言われることもあります。
映画の中でも、女形の役者が自身で化粧を施し、着物を身にまとって舞台上で輝く姿が丁寧に描かれています。
主題歌の美しさ×歌舞伎の美しさが生み出す感動
「国宝」の主題歌である『Luminance』は、エンドロールに流れます。楽曲に歌唱で参加している井口理氏は、King Gnuのボーカル・キーボード担当で、実際に声楽(クラシック音楽の歌唱法)を学んだ経歴を持つことで有名です。
エンドロールのあいだ、ほとんどの人が席を立たずに終わりまで座っていました。歌唱の儚さと、さっきまで観ていた歌舞伎界の儚さはどちらも美しく、しばらく放心状態になってしまいました。
血縁と芸の継承
屋号や名跡を継ぐ血筋や師弟の関係性も、歌舞伎界の重要な要素です。何百年もの間受け継がれてきた芸の系譜は、単なる血縁関係を超えた深い精神的な繋がりによって支えられています。師匠から弟子へ、父から息子へと受け継がれる技術や心構えは、言葉では表現しきれない重みを持っています。
映画では、そうした継承の重圧と責任、そして誇りを背負う役者たちの内面も繊細に描写されています。名前を継ぐということの意味、先代への敬意、次の世代への責任。これらの複雑な感情が、役者たちの演技を通じて体感できたような気がします。
歌舞伎ならではの舞台演出
早変わりや花道といった独自の舞台演出は、歌舞伎ならではの見どころです。一瞬のうちに衣装や化粧を変える早変わりの技術、客席を縦断する花道での印象的な登場や退場、このような演出は、観客を物語の世界へと一気に引き込む魔法のような力を持っています。
舞台演出のほかにも、観客が参加する「掛け声」も、歌舞伎独自の文化です。歌舞伎の舞台で、客席からかけられる掛け声を「大向こう(おおむこう)」と言います。 観客が「成田屋!」や「中村屋!」といった屋号(歌舞伎役者の家ごとの名前)を叫んだり、決めの入った場面で「よっ!」という掛け声を入れたりすることで、舞台を盛り上げる役割を担います。舞台と客席が一体になって作り上げる特別な空間が歌舞伎のもつ魅力のひとつです。
現代に生きる伝統の意味
この映画を観て改めて考えさせられたのは、伝統芸能が今の社会において、どんな意味を持っているのかということでした。
グローバル化やAIの凄まじい進化によって、日本のエンターテインメントも日々多様化しています。そんな中で、400年以上の歴史を持つ歌舞伎が、いまもなお多くの人を惹きつけるのは何故なのでしょうか。
その理由は、歌舞伎がただの古典芸能ではなく、人間の感情や体験を受け継いできた「生きた芸術」だからではないかと思います。
歌舞伎の演目には、美談よりもむしろ、恨みや嫉妬、欲望など、人間の生々しい感情を描いたものが多くあります。
愛や憎しみ、嫉妬、名誉、裏切りといった情念は、時代を超えて人の心にあり続けるものです。江戸時代の人も、私たち現代人も、そうした感情と向き合いながら生きているのだと、歌舞伎を通じて改めて感じさせられます。
たとえ社会がどれほど変わっても、人間の本質は変わらない。そんな普遍性を感じられるところが、歌舞伎の大きな魅力なのかもしれません。
映画「国宝」は、そうした歌舞伎の持つ人間くさい普遍性と美しさを、見事に現代の映像作品として再構築した作品と言えるでしょう。
気になった方はぜひ、ご覧になってみてください!
(大変に長編のため、観に行く際は準備が大切です💦)