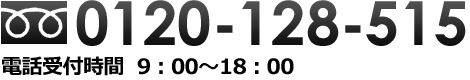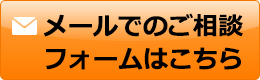「ここが、どうしても分からないんです。」
そう言われて、少し話を聞いてから尋ねてみる。
「仕様書、読んでみた?」
そして返ってくるのは、だいたいこんな言葉。
「読んでないです。仕様って難しそうで……」
これは、駆け出しのエンジニアから本当によく聞く言葉です。”一時情報を咀嚼する作業” なんてすっ飛ばしたくなるその気持ち、すごくよく分かります。仕様書って長いし、言い回しも独特で小難しいし、英語だったりして、一発で理解できるものじゃありません。初めて開いたときに「うわ、むり」と思うのは自然な反応だよなぁ。
だからつい、「解説記事のほうが早い」「とりあえず動けばいい」と考えてしまいがちなんですよね。ネットには便利な情報がたくさんあって、検索すればすぐに“正解っぽい答え”にたどり着ける。私だってその恩恵に助けられてきました。
でも、ふと考える瞬間があります。
最適解を探すことに必死になりすぎてないか? と。
最適解よりも、根拠を知るほうが近道のときもある
最速で正しい答えに辿り着きたい気持ちは、よく分かります。でも、答えを急ぐあまりに理解のプロセスを飛ばして、あらぬ方向へ進んでしまうことだってあります。
逆に、仕様を知っている人は、検索の旅が短いです。情報の信頼度を自分で判断できるし、「なぜ」を理解しているから応用も効く。
根拠を持って判断できる人は、強いです。
Webは仕様によって動いている
HTML も CSS も JavaScript も、そしてブラウザの挙動までも、すべて「仕様」に書かれています。普段なにげなく使っているタグやプロパティ、メソッドには、ちゃんと意味や背景があって、それに従って動いています。簡単な具体例を、いくつか挙げてみましょう。
具体例1:<strong> と <b>
どちらも太字になりますが、意味はまったく違います。<strong> は「重要性」を示し、スクリーンリーダーの読み上げ方にも影響します。一方 <b> は見た目の強調にすぎません。見た目は同じでも、意図は全然違うんですよね。
具体例2:loading=”lazy” の読み込みタイミング
画像の遅延読み込みで loading=”lazy” を使うと、ブラウザによって読み込みタイミングが微妙に違います。検索すると「ブラウザ差です」と説明されて終わることが多いですが、仕様には “読み込みタイミングはブラウザの判断に任せる” と書かれています。なぜタイミングが微妙に違うのか、その原理を知っているだけで、無駄な検証をせずに済むことも。
具体例3:JavaScript の == と ===
これも有名な話ですが、「なんか怖いから === 一択で 」で済ませられがちです。
でも、== がなぜ危ないのか、本当のところは仕様の “抽象的等価比較アルゴリズム” に書かれています。
「なんとなく避ける」から「なぜ避けるべきかを知って選択する」へ変わると、自分の中で技術が腹落ちしていく感覚が味わえるかもしれません。
「なにこれ、めちゃくちゃ腑に落ちる」を体験してほしい
仕様を読んでも、すぐに全部が理解できるわけではありません。むしろその逆で、難解な文字列にウンザリするかもしれません。でも、少しずつ読み進めて、ある日突然「あ、これそういうことか」と理解がつながる瞬間があります。
そのときの感覚、けっこうクセになると思うんですよね。
誰かの答えをコピペして動作した瞬間の嬉しさとは、少し種類が違います。回り道に見えた時間が、あとから一気に報われる感じです。
仕様を読むのは、たしかにしんどいです。でも、その中には確かな理解があります。もし今日、ほんの数分だけ時間があるなら、興味のある言語や、今触っている技術のページをひとつだけ開いてみてください。「へぇ、こういうことなんだ」と、ほんの少しだけ視界を広げる一歩になるはずです。